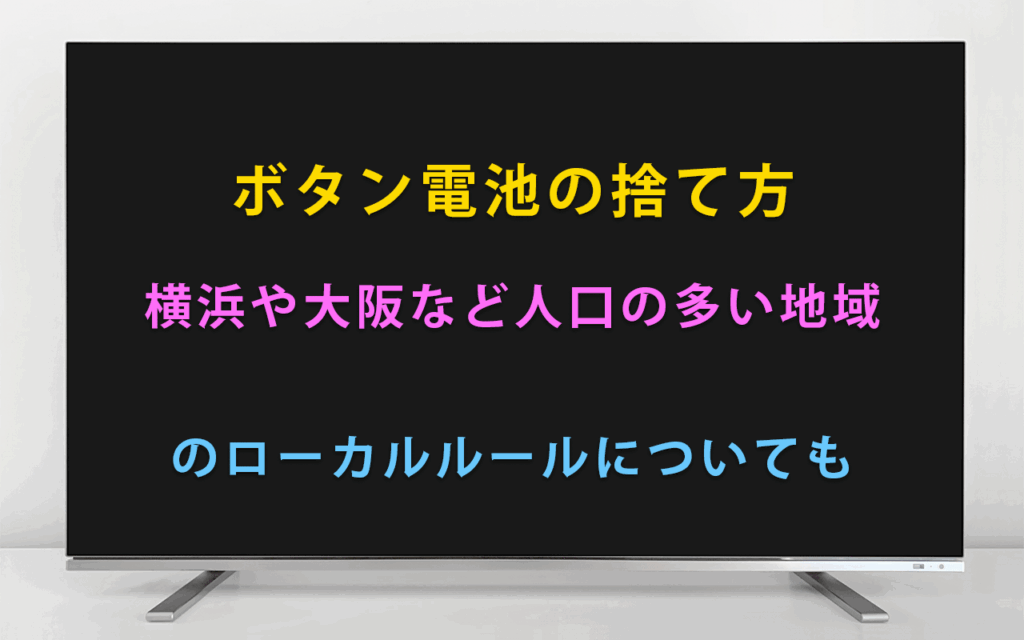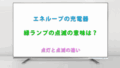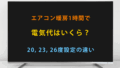「ボタン電池をどう捨てたらいいかわからない」「自治体によってルールが違う」と感じる方は多いはずです。
しかし、ボタン電池の捨て方は、たった3つのステップで安全かつ確実に判断できます。
この記事では、
ボタン電池の捨て方について、火災事故を防ぎ、環境を守るために、全国共通のルールと、横浜市や大阪市といった大都市圏で特に注意すべきローカルルールを、初心者の方にもわかりやすく解説します。
なぜボタン電池の捨て方は重要なのか?
ボタン電池の処分が厳しく定められている主な理由は2つあります。
これは単なるルールではなく、私たち自身の安全と環境を守るための重要なルールです。
1. 火事になる危険:ショート(短絡)を防ぐ
ボタン電池は小さいながらも電気を持っています。
そのままゴミとして他の金属や電池と混ざると、電気が流れすぎて熱を持ち、火災(ショート)の原因になります。
近年、全国のゴミ処理施設や収集車で、このショートによる火災が急増しており、大変危険です。
ボタン電池は、比較的に省電力ですが、万全を期して処分しておいた方が良いです。
2. 環境を守る義務:過去の製品に含まれる水銀の管理
一部の古いボタン電池には、環境に有害な水銀が微量に含まれていました。
現在、販売されているボタン電池は無水銀化されていますが、古い製品がまだ市場に残っているため、それらを安全に回収し、水銀が環境に流出するのを防ぐ義務があります。
3ステップで完了!ボタン電池の安全な捨て方
あなたのボタン電池が「自治体のゴミ」なのか「回収協力店行き」なのかを判断するための、簡単な手順です。
ステップ1:最重要!ボタン電池の両端をテープで絶縁する
どの種類の電池であっても、地域ルールに関わらず、絶縁処理は絶対に行うべき必須の安全対策です。
- 用意するもの: セロハンテープ、またはビニールテープ。
- 絶縁方法: 電池のプラス極(+)とマイナス極(-)の両方を、テープで完全に覆い隠します。
- 電池が金属に触れてショートするのを防ぐため、側面にもテープを回し、金属部分を露出させないようにすると、より安全です。
- 保管: 絶縁した電池は、他の金属や電池類と接触しないよう、小さなプラスチック容器などに入れて保管しましょう。

ステップ2:電池に刻まれた「型式記号」を確認する
ボタン電池を裏返すと、「SR」「PR」「LR」「CR」「BR」といったアルファベットと数字が刻まれています。
この記号が、捨てる場所を決めるカギになります。
| 型式記号 | 電池の種類 | 主な用途 | 水銀リスク | 処分のルート |
| SR、PR、LR | 酸化銀、空気、アルカリ | 時計、補聴器、電子体温計など | あり(旧製品) | 回収協力店(メーカー回収) |
| CR、BR | リチウムコイン電池 | リモコン、車のキー、PCのバックアップなど | なし | 自治体の不燃ごみ等 |
ステップ3:ボタン電池の処分のルートを選ぶ
電池の種類によって廃棄予定のボタン電池の処分ルートを選びます。
SR, PR, LR型の場合:回収協力店へ持ち込み
これらの電池は、過去に水銀を含んでいたリスクがあるため、環境大臣の認可を受けたメーカー団体(一般社団法人電池工業会:BAJ)が責任を持って回収・リサイクルします。
- 出し方: ステップ1で絶縁処理をした上で、「ボタン電池回収缶」が設置されている近隣の回収協力店(家電量販店、時計店、補聴器店など)のスタッフに渡します。
- 協力店の探し方: インターネットで「電池工業会 回収協力店」と検索するか、販売店に問い合わせてください。
CR, BR型の場合:自治体のゴミとして排出
これらのリチウムコイン電池は水銀を含んでいないため、メーカー回収(BAJ)の対象外です。
出し方:
ステップ1で絶縁処理をした上で、お住まいの自治体が定める不燃ごみなどのルールに従って排出します。
ボタン電池の捨て方:大都市圏(横浜、大阪、名古屋、東京)のローカルルール
多くの自治体は上記(ステップ3)の原則に従いますが、人口が多い大都市圏では、安全性を高めるために独自の特殊なルールを設けている場合があります。
名古屋市:全ての電池を「一括収集」する独自ルール
名古屋市は、市民の分別を簡略化し、危険な電池の混入を防ぐため、ボタン電池(SR/PR/LR, CR/BR)、乾電池、モバイルバッテリーなど、ほぼ全ての電池類を市がまとめて収集しています。
横浜市:2025年12月からルールが大きく変わる予定
横浜市は、2025年12月1日から、従来の乾電池に加え、モバイルバッテリーやボタン電池など全ての電池類を、新設する「電池類」として市が収集する予定です。
- 現行ルール(2025年11月まで): 市の資源循環局に確認し、SR/PR/LR型は回収協力店(BAJ)を利用することが推奨されます。
- 今後の対応: 制度移行期(2025年12月以降)に向けて、横浜市民の方は市の最新情報を必ず確認してください。
3. 東京23区(例:練馬区、世田谷区):基本原則を徹底
東京23区の多くの区では、全国共通の原則が適用されます。
- SR/PR/LR型: 回収協力店(BAJ)へ持ち込み 。
- CR/BR型: 絶縁した上で、区の不燃ごみとして排出 。
4. 大阪市・福岡市:迷ったら「回収協力店」を優先
大阪市のよう自治体では回収していなかったり、ルールが不明確な自治体の場合、安全を最優先してください 。
- 水銀リスクのあるSR/PR/LR型は、必ず回収協力店(BAJ)を利用します。
- CR/BR型や乾電池については、自治体の担当部署(環境局など)に直接問い合わせて確認するのが最も安全です。
まとめ:ボタン電池の捨て方ローカルルールも
ボタン電池の捨て方は、火災事故や環境汚染を防ぐために非常に重要です。
基本は「①必ず絶縁処理をする」「②型式記号を確認する」「③処分ルートを選ぶ」という3ステップで完了します。
水銀を含む可能性のあるSR・PR・LR型は回収協力店へ、CR・BR型は絶縁した上で自治体のルールに従い廃棄します。
ただし、名古屋市のように独自の「一括収集ルール」や、横浜市のように今後制度変更を予定している自治体もあるため、お住まいの地域の最新情報を確認することが欠かせません。
正しい処分を行うことは、自分や家族の安全を守るだけでなく、ごみ収集現場で働く方や環境全体を守ることにつながります。
今日から実践できる小さな習慣として、ぜひ意識してみてください。