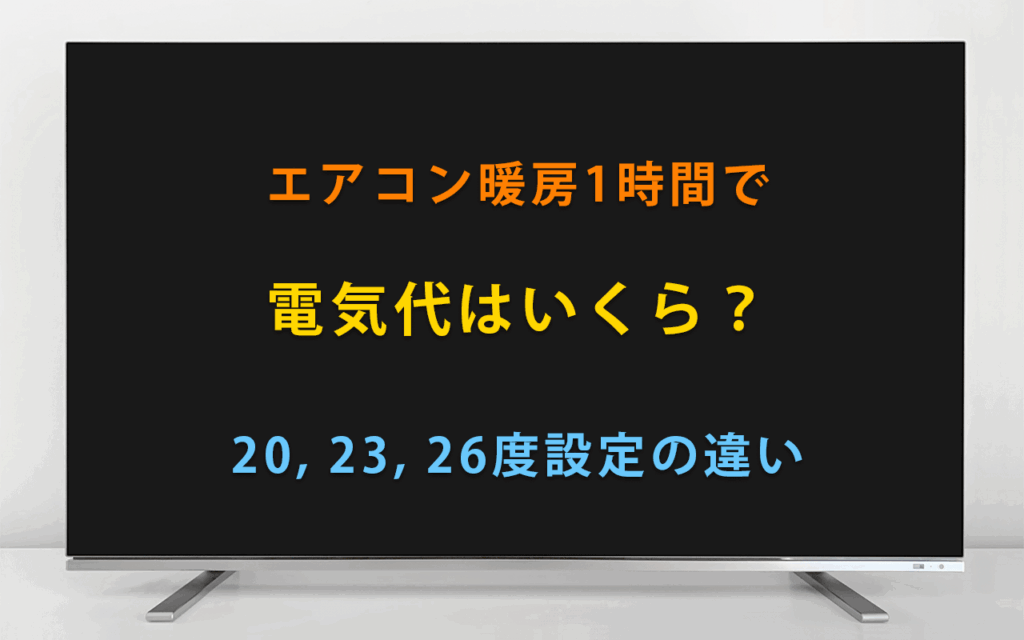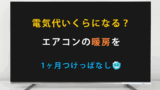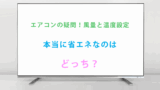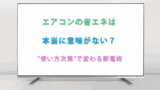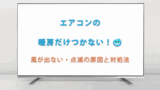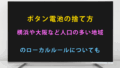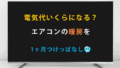冬の暖房シーズンになると、「エアコンを1時間使うと電気代はいくらかかるの?」と気になる方は多いでしょう。
特に、20℃・23℃・26℃と設定温度を少し変えるだけで、電気代はどのくらい増えるのかは、家計に直結する重要なポイントです。
さらに、部屋の広さや断熱性、外気温によってもコストは大きく変わります。
本記事では、エアコン暖房の1時間あたりの電気代を温度別・部屋のサイズ比較し、節約につながる裏技や「つけっぱなし vs. ON/OFF」の正しい使い方まで徹底解説します。
無理に我慢せず、快適さを保ちながら効率よく節約できる方法を一緒に見ていきましょう。
エアコン 暖房1時間あたりの電気代はいくら?20, 23, 26度の比較
エアコンの暖房を1時間稼働させた時の電気代は温度が20度、23度、26度と高くなるほどコストも高くなります。
多くの人が設定する目安である20度、23度、26度を基準に電気代の傾向を解説します。
「1℃」の重みがあなたの財布を直撃する
まず結論からお伝えします。
エアコン暖房において、設定温度をたった1℃下げるだけで、消費電力(電気代)は約10%も節約できると言われています。
逆に言えば、寒くないのに1℃上げてしまうと、電気代が10%増えてしまうということです。
この「1℃=10%」の法則に基づき、環境省が推奨する目安温度の20℃と、それより3℃、6℃高い場合の電気代を比較しました。
1時間あたりの電気代の目安(※31円/kWhで計算)
| 設定温度 | 1時間あたりの電気代 | 20℃からの増加率 |
| 20℃ (推奨目安) | 約14円 | 基準 (0%) |
| 23℃ (+3℃) | 約18.6円 | 約33%増 |
| 26℃ (+6℃) | 約24.7円 | 約77%増 |
もし、毎日8時間エアコンを使い、これを30日間続けたと仮定すると、その差は月々約2,580円にもなります。
エアコンの暖房を使う期間が4ヶ月だとしても、設定温度をわずかに変えるだけで、年間で1万円以上の節約効果が生まれるのです。
なぜ暖房は電気代が高いのか?(エアコンの仕組みを解説)
なぜ、夏よりも冬の暖房の方が電気代が高くなりがちなのでしょうか。
その理由の一つには、外との温度差にあります。
冬の朝、外の気温が5℃で、あなたが設定したい温度が25℃だとすると、その温度差は20℃もあります。
これに対して、夏場は外気温35℃、設定温度28℃だと差は7℃程度です。
エアコンは、この大きな温度差(これを「熱負荷」と呼びます)を埋めるために、より強い力で長時間運転し続けなければなりません 。
これが冬の電気代高騰の最大の原因です。
インバーター制御の秘密:急発進が一番お金がかかる
最近のエアコンには「インバーター」という賢い制御機能が搭載されています。
これは、車でいうアクセル調整のようなものです 。
- 立ち上がり運転(急発進):
部屋が冷え切っている時、設定温度まで一気に温めるため、エアコンは最大出力(例えば800Wなど)で「急発進」します。この時、最も多くの電力を消費します。 - 安定運転(クルーズ運転):
設定温度に近づくと、エアコンはゆっくりと回転数を落とし、少ない電力(例えば300W〜450W)で温度を「キープ」する運転に切り替わります。
この状態が最も節約できています。
つまり、設定温度を高くすればするほど、この「キープ」状態に持っていくまでに時間がかかり、さらに外との温度差が大きいほどキープし続ける力も必要になるため、電気代が高くなるのです。
我慢せずに節約できる「3つの裏技」
設定温度を20℃にするのが節約の基本ですが、寒さを我慢する必要はありません。
以下の3つの「効率化」の裏技を使えば、体感温度を上げて快適に過ごしながら、電気代を抑えることができます。
裏技①:暖房の熱が逃げる「窓」を死守する
せっかく温めた部屋の熱は、どこから逃げていると思いますか?
実は、熱損失の約58%が窓などの開口部から逃げています。
【対策】
- 厚手のカーテンを使いましょう。
- 床まで届く長さのカーテンを閉めるだけで、窓から逃げる冷気や暖気をブロック
- 古いアルミサッシの窓であれば、断熱シートを貼るのも効果的です。
冷気は空気が重く下からくるのでこう言った製品もあります。
*温度を温める効果があるわけではないので、体感としては1℃程度ぐらいしか差を感じないかもしれません。しかし、電気代の観点ではその1℃が大きな効果になります。
裏技②:サーキュレーターで暖かい空気をかき混ぜる
暖かい空気は性質上、部屋の天井付近に溜まりがちです。
床や足元は冷たいのに、天井の温度計が設定温度に達すると、エアコンは「もう温まった」と判断して運転を弱めてしまいます。
これが「設定温度は高いのに、足元が寒い」と感じる原因です。
【対策】
サーキュレーター(扇風機でも可)をエアコンの反対側の壁や、部屋の中心に置き、天井に向けて上向きに回しましょう。
これにより、天井に溜まった暖かい空気が部屋全体に循環し、温度ムラがなくなり、設定温度を上げなくても暖かく感じられます。
サーキュレーター自体の電気代は非常に安価です。
裏技③:加湿器で体感温度を上げる
冬の乾燥した空気の中では、体感温度が下がってしまいます。
夏に湿度が高いと蒸し暑く感じるのと同じ原理で、冬も湿度を適切に上げると体感温度が上がり、暖かく感じられます。
【対策】
加湿器を併用し、湿度を50%〜60%に保ちましょう。
これにより、物理的な設定温度を少し下げても寒く感じにくくなり、節約につながります。
財団法人省エネルギーセンターの試算では、加湿を併用することで、1℃の節約効果が得られるとしています。
知っておきたい「つけっぱなし vs. こまめなON/OFF」
「電気代を節約するために、部屋を出るたびにエアコンを切るべきか?」という質問はよくあります。
インバーターエアコンの場合、前述の通り、最も電力を使うのは「立ち上がり運転(急発進)」の瞬間です 。
結論:
30分から1時間程度の短い外出や離席なら、電源を切らずに「つけっぱなし」の方が節約になる可能性が高いです。
これは、安定運転で低い電力をキープし続けた方が、何度も急発進させる電力よりも安くなるためです。
ただし、長時間(数時間以上)家を空ける場合は、もちろん電源を切って問題ありません。
要は、「急発進」の回数をいかに減らすかが、節約の鍵となります。
エアコン設定 20度:【国が推奨するルール】と【機械の最適効率】
20℃は、これが国が定めた節電の「目標温度」だからです。
- ウォームビズの目標:
環境省や資源エネルギー庁が冬の暖房設定の目安として20℃を推奨しています。
これは、快適性を保ちつつ、エネルギー消費を抑えるための公式な基準です。 - 機械にとって最も効率的:
エアコンの技術的なテストや効率を測る基準(JIS規格など)でも、暖房時の室内温度は20℃を前提としています。
つまり、20℃は「ルールであり、かつ、機械が最も力を発揮しやすい(効率が良い)温度」なのです。
「国が推奨する20℃で本当に寒くないか?」
「20℃に設定するのが一番お得なのか?」
そんな疑問にお答えするために比較値としました。
エアコン設定 23度:【体が求める快適さ】(20℃からの逃避)
20℃が公式なルールだとしても、多くの人にとっては少し寒いと感じる境界線です。
- 生理的な快適点:
人の体感温度や健康を考えると、20℃ではまだ肌寒いと感じる人が多く、無意識にもう少し高い温度を求めがちです。 - 3℃の葛藤:
20℃は節約できるが寒い。かといって、高くしすぎると電気代がかさむ。その結果、多くの人が「節約のルール(20℃)から少しだけ妥協して快適さを求める(23℃)」という選択をします。
「20℃だと寒いから23℃にしたいけれど、電気代はどれくらい増えるのだろう?」「23℃に設定しても許されるだろうか?」という快適さとコストの間の葛藤の温度である23℃を比較の数値としました。
エアコン設定 26度:【夏の習慣】と【社会的な妥協点】
26℃は、暖房の設定温度としては高すぎますが、「冷房(夏)の鉄板設定」として非常に強く根付いています。
- 夏の公式目標は28℃:
国は夏場に「クールビズ」で28℃を推奨していますが、多くのオフィスや家庭では「28℃だと暑すぎて仕事や生活に支障が出る」と感じています。 - 実用的な妥協点:
多くのオフィスビルや商業施設、家庭が、28℃のルールを避け、実用的で納得できる「26℃」を夏の標準設定として採用される傾向があります。(特に若い男性が好む)
この「26℃=設定して当たり前の温度」という習慣が強いため、冬の暖房に関する疑問にも温度の比較値として取り扱いました。
エアコン 暖房1時間あたりの電気代はいくら?部屋のサイズが与える影響
畳数が大きいほど「暖める力」が必要になる
エアコンは、設定された温度(今回の場合は20℃、23℃、26℃)に到達させ、その温度を維持するために動いています。
部屋のサイズが大きくなると、当然ながらエアコンが温めなければならない空気の量(体積)が増えます。
つまり、エアコンは、設定温度に到達するために、部屋の広さに比例してより多くの電力を消費することになります。
部屋の広さによる1時間あたりの電気代の目安
一般的な家庭用エアコン(暖房時)の1時間あたりの電気代の目安を、畳数別に比較すると、その影響度が明確になります。
| お部屋の広さ(畳数) | 1時間あたりの電気代の目安(円) |
| 6畳 | 約15円 |
| 10畳 | 約19.3円〜21.9円 |
| 14畳 | 約27円 |
| 18畳 | 約42.7円〜42.9円 |
出典:複数の調査結果より、31円/kWhで換算した安定運転時の概算 。
部屋の広さと設定温度の関係
電気代が高くなるリスクは、「設定温度」と「部屋の広さ」が組み合わさることでさらに増幅されます。
- 「容量不足のエアコン」で広すぎる部屋を暖める場合
- 例えば、10畳用のエアコンで18畳の部屋を温めようとすると、エアコンは常に最大出力(立ち上がり運転)に近い状態で稼働し続けることになり、いつまでも「安定運転」に入れず、電気代が最も高くなるパターンに陥ります。
- 「広い部屋」で「26℃」を設定した場合
- 単純に部屋が広いだけでも電力を消費しますが、26℃という外気温との大きな差を埋めようとすることで、最大出力での運転時間が長引き、電気代がさらに跳ね上がります。
エアコンを選ぶ際は、部屋の広さに合った容量の機種を選び、冬場は室外気温が低いため、推奨畳数より余裕のある機種を選ぶことが重要です 。
部屋のサイズ以外にも影響する要因
部屋の広さ以外にも、電気代の効率を左右する重要な要因が2つあります。
断熱性・気密性
古い木造住宅や、窓が多く断熱性が低い部屋は、せっかく温めた熱がどんどん外に逃げてしまいます(特に窓からの熱損失は全体の約58%)。
この場合、エアコンは失われた熱を補うため、設定温度を低くしても高負荷で運転し続ける必要があり、電気代が高くなります。
高気密・高断熱の住宅では、室温が安定しやすく、エアコンは最小限の電力で運転をキープできるため、電気代の節約につながります。
外気温
外気温が低ければ低いほど、室温との温度差が大きくなるため、電気代が高くなります。
例えば、外気温が0℃の日と10℃の日では、同じ設定温度でも電気代は大きく異なります。
まとめ:エアコン 暖房1時間あたりの電気代はいくら?
エアコン暖房の電気代は、「設定温度」「部屋の広さ」「断熱性や外気温」といった要因で大きく変わります。
特に「1℃上げる=約10%の電気代増」というルールを意識するだけでも、年間で1万円以上の節約が可能です。
また、つけっぱなしとこまめなON/OFFの使い分けや、窓の断熱・サーキュレーター・加湿器といった工夫を組み合わせれば、寒さを我慢せずに快適さと節約を両立できます。
エアコンを賢く使いこなすことが、冬の光熱費を抑える最大のポイントです。
関連記事