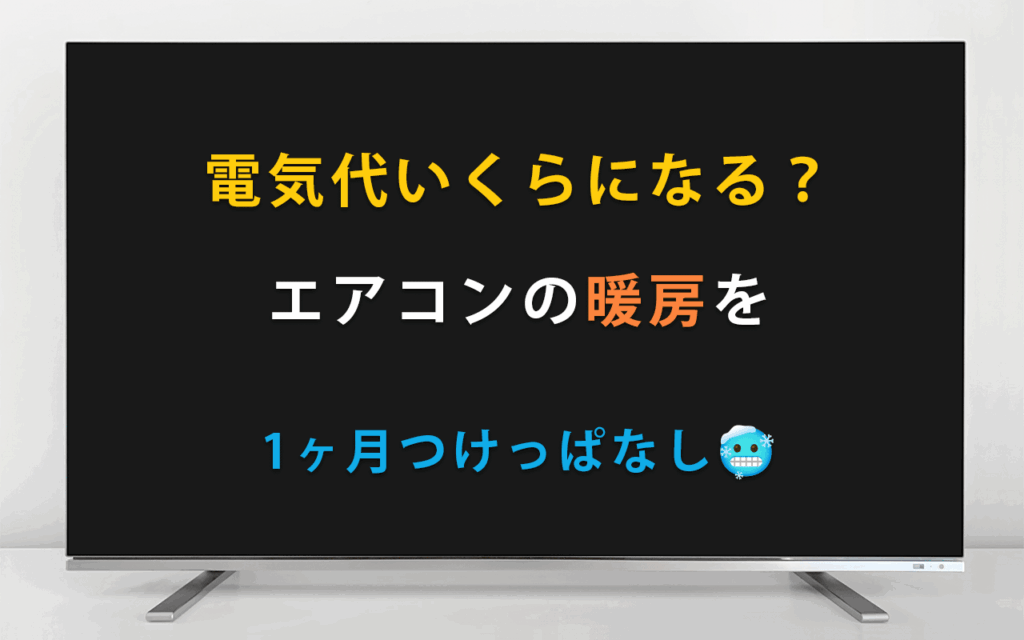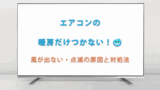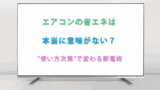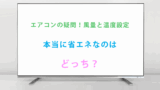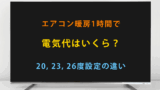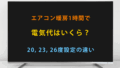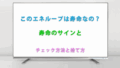冬場、エアコンの暖房を長時間使用することに対する家計の不安は非常に大きな関心事です。
特に在宅勤務の増加やライフスタイルの変化により、エアコンの稼働時間が過去に例を見ないほど伸びています。
本記事でわかる事
「暖房を1ヶ月(30日間)つけっぱなしにした場合の具体的なコスト」を試算します。
を明確に解説します。
さらに、初心者でも今日から実践できる、具体的な節約テクニックを深く掘り下げて解説します。
エアコンの暖房を1ヶ月(30日)つけっぱなしの電気代は?
エアコン暖房のコストを正確に把握するために、24時間連続運転(つけっぱなし)を1ヶ月行った場合の電気代のシミュレーション結果を提示します。
試算の前提として、昨今の電力料金は小売電力単価だけでなく、使用量に応じて加算される「再エネ賦課金」も考慮に入れる必要があります。
2025年度(2025年5月分から2026年4月分まで)の再エネ賦課金単価は3.98円/kWhに設定されています。(ちなみに2024年は3.49円/kWh)
単価の出所:経産省再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2025年度以降の買取価格等と2025年度の賦課金単価より
一般的な電力単価目安である31円/kWh と合わせると、
実質的な電力単価は
31円/kWh + 3.98円/kWh = 34.98円/kWhとなります。
新型と旧型で見るコストの差(24時間連続運転)
エアコンの消費電力は、機種の新旧によって大きく異なります。
特に、インバーター制御や省エネ性能が向上している新型機種は、旧型に比べて定格消費電力が低い傾向にあります。
以下の表は、定格消費電力の目安に基づき、24時間つけっぱなし運転を継続した場合のコストを示しています。
定格消費電力とは
すべての機能を最大限に使った場合に消費される最大消費電力量のこと。
定格消費電力の「定格」は、国家規格である日本工業規格(JIS規格)に基づいた条件下で、その電化製品を連続して使った場合に安定して出力できる力を指す「定格能力」を表す。
月間(30日)エアコン暖房つけっぱなしの電気代目安 (24時間運転)
| 機種区分 | 定格消費電力の目安 (W) | 1日あたりの電気代目安 (円) (※34.98円/kWh換算) | 1ヶ月あたりの電気代目安 (円) |
| 新型(省エネ) | 500W | 約420円 | 約12,593円 |
| 旧型 | 700W | 約588円 | 約17,630円 |
この試算結果から明らかになるのは、新型と旧型では、つけっぱなしにした場合、月間でおよそ5,000円、冬の暖房期間(仮に4ヶ月)では約2万円ものコスト差が発生するという事実です。
この大きな差額は、単なる「節約努力」で埋められるものではありません。
旧型を使い続けることは、年間数万円に及ぶ「目に見えない罰金」を払い続けているのと同義であり、このデータは、省エネ性能の高い新型機種への買い替えが、長期的な視点で見ると合理的な「設備投資」であることを強く示唆しています。
部屋の広さ別シミュレーション(定格運転時)
エアコンは、部屋の広さ(畳数)に応じて必要な暖房能力が変わり、それに伴い消費電力も増加します 。
無理に小さなエアコンで広い部屋を温めようとすると、エアコンは定格運転(最も効率の良い運転)ではなく、高い消費電力が必要な最大能力運転を強いられるため、結果として試算値よりもコストが高くなるリスクがあります。
例えば、暖房時の標準(定格)消費電力で見ると、6畳用で440W、10畳用で660W、14畳用では1,060Wが必要とされており、部屋が広くなるほど、運転に必要な電力は直線的に増加します。
自分の部屋の広さに合った適切な能力のエアコンを使用することが、効率的な暖房の第一歩です。
なぜ電気代は変動し、どう計算されるのか?
電気代の変動要因を理解するためには、電力の基本的な単位と、電気料金の構造を把握することが不可欠です。
「W」「kW」「kWh」の役割
電気代は、消費電力と使用時間、そして料金単価によって決まります。
この関係性を理解するためには、以下の単位を知る必要があります。
- W(ワット): 瞬間に使用する電力の大きさ(消費電力)を示します。
- kW(キロワット): 1,000Wのことです。電力の計算ではこの単位がよく用いられます。
- kWh(キロワットアワー): 消費電力(kW)に、その電力をどれだけの時間(h)使ったかをかけた値です。電気料金の計算はすべてこの「kWh」単位で行われます。
エアコンの運転中は、設定温度に近づくと消費電力(W)が下がり、設定温度から離れるとWが上がります。
この変動する消費電力を積算したものが電気使用量(kWh)となり、これが電気代の基礎となります。
見逃してはいけない「電力料金単価」の真実
電気料金は、単に「電力量料金(例:31円/kWh)」だけで構成されているわけではありません。
電気料金の総額は、主に以下の3つの要素で構成されています 。
- 基本料金
- 電力量料金(使用量:kWhに基づいて計算される)
- 燃料調整費(FAF)と再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)
特に注目すべきは、燃料調整費と再エネ賦課金です。
燃料調整費(FAF)
燃料調整費は、火力発電に必要な燃料(原油、石炭、LNGなど)の市場価格の変動を、電気料金に反映させるための仕組みです。
市場価格が下がればマイナス(割引)になることもありますが、上がり基調であればプラス(割増)となります。
この単価は旧一般電気事業者ごとに月ごとに発表されます。
再エネ賦課金(RES):高使用量者が特に注意すべき固定コスト
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を支援するために、全ての電力需要家が電気の使用量に応じて全国一律の単価で負担するものです。
これは使用量(kWh)に比例して課金されるため、24時間つけっぱなしのような高使用量(高kWh)運転を行うほど、この賦課金の負担額も比例して増大します。
2025年度の単価は3.98円/kWhであり 、この単価は再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、年々上昇傾向にあることが示されています。
したがって、つけっぱなし運転で消費電力量が増加すると、小売電力単価だけでなく、この賦課金による「隠れた固定コスト」も加算されるため、総請求額は単純計算以上に膨らむことになります。
冷房時よりも暖房時の方が電気代が高くなる理由
一般的な認識として、エアコンの運転は冷房時よりも暖房時の方が多くの電力を消費し、電気代が高くなる傾向にあります。
この消費電力の差の主な原因は、外気温と設定温度の差が大きいことです。
夏場の冷房では、外気温(約30℃)と設定温度(約28℃)の差はわずかですが、冬場の暖房では、外気温が低く設定温度(推奨20℃)との間に大きな差が生じます。
この大きな温度差を埋めるために、エアコンの心臓部である圧縮機が長時間フル稼働せざるを得ず、消費電力量が大幅に増加します。
「つけっぱなし」と「オンオフ」の決定的な境界線
「エアコンはつけっぱなしの方が安い」という説は広く流布していますが、これは特定の条件が揃った場合にのみ当てはまるものであり、万能な節約術ではありません。
なぜ起動時に電力を大量に消費するのか?
エアコンが最も電力を消費するのは、室温を設定温度まで急速に引き上げる「起動時(立ち上げ時)」です。
特に冬の暖房では、外気温が低く、設定温度(20℃程度)との差が大きいため、冷房時よりもこの立ち上げに要する電力が大きくなります。
つけっぱなし運転のメリットは、室温が設定温度に達した後、低電力で温度を維持する「定格運転」の状態を長く保つことにあります。
これにより、頻繁に高電力を使う「起動時」を避けることができるため、節約につながる可能性があります。
外気温3℃ルールと住環境による最適解
つけっぱなしとオンオフのどちらが有利かを判断する決定的な境界線として、パナソニックが提唱する「外気温3℃ルール」があります。
ルール: 外出時間が1〜2時間程度の場合、外気温が3℃以下であれば、つけっぱなし運転を行った方が電気代は抑えられる可能性が高いです。
適用条件の解説
この3℃という基準は、外気温が非常に低く、室温が急激に下がってしまう環境を想定しています。
外気温が3℃を下回ると、一度エアコンを切って再稼働する際に、室内を再加熱するために極めて大きな電力(フルパワー)が必要になるためです。
しかし、このルールには住環境による例外が存在します 。
- つけっぱなしが有利なケース(◎):
- 高断熱住宅: 住宅の断熱性が非常に高く、熱が逃げにくい場合 。
- 在宅時間が非常に長い: 一日の中で数時間の不在が少ないファミリーや、常に在宅している場合 。
- こまめなオンオフが有利なケース(◎):
- 断熱性が低い住宅: 築年数が古い、または断熱対策が不十分で、熱がすぐに逃げてしまう住宅の場合 。
- 一人暮らしや外出が多い: 1〜2時間以上の外出が多い場合 。
- 旧型機種: 旧型のエアコンはインバーター制御が劣るため、定格運転(安定運転)に入りにくく、つけっぱなしによるメリットを享受しにくい 。
日本の多くの都市部(例えば東京都の1月平均気温は概ね5℃〜7℃前後)では、3℃の壁を上回ることが多いため 、 一般的な断熱性の住宅で短時間(1〜2時間)の外出をする場合は、こまめに切る方が有利になる可能性が高いと分析されます。
自身の居住環境の断熱性と地域の気温を冷静に考慮し、無闇な「つけっぱなし神話」を信じるべきではないと結論付けられます。
20度と28度の違い:暖房1ヶ月つけっぱなしの電気代の差は?
「28度」という温度は、夏の冷房使用時に推奨される「クールビズ」の目安として広く知られています。
環境省などが推奨する暖房時の室温は20℃です。
これに対し、28℃という設定は極めて高く、暖房効率が大幅に低下し、電気代が跳ね上がることが予想されます。
あえて、比較してみると
シミュレーション前提(新型エアコン・つけっぱなし運転)
- 基準単価(2025年度): 34.98円/kWh (電力単価31円/kWh + 2025年度再エネ賦課金3.98円/kWh)
- 基準消費電力: 新型(省エネ)モデルの定格消費電力500Wを採用
- 20℃設定時の月間コスト(基準): 約12,593円
28℃設定時の推定月間コスト
設定温度を1℃上げるごとに約10%の電気代が上昇すると仮定すると、20℃から28℃へ8℃上昇させた場合の理論的な電気代の増加率は、概ね以下のようになります。
| 設定温度 | 20℃設定時の月間コスト (新型) | 28℃設定時の推定増加率 (8℃上昇) | 28℃設定時の推定月間コスト | 月間コスト差 |
| 20℃ | 約12,593円 | 基準 (0%) | 約12,593円 | – |
| 28℃ | 約12,593円 | 80%増 | 約22,667円 | 約10,074円 |
結論として、新型エアコンを1ヶ月つけっぱなしにした場合、設定温度を20℃から28℃に上げただけで、理論上は月間約1万円ものコストが増加する可能性があります。
これに「部屋の広さ」や「外気と室内の差」が影響を与えるとさらに電気代は高くなります。
そもそも推奨温度が暖房(20度)と冷房(28度)のように違う?
環境省は省エネ推進の観点から、冷房時28℃、暖房時20℃という数値を提唱されています。
私たちが夏によく聞く冷房の推奨温度「28℃」は、実は「快適さのゴール」というよりも、「これ以上下げすぎないでね」という、国や社会全体で取り組む「省エネのための努力目標」の意味合いが強いです。
地球温暖化対策や電力消費の抑制を目的とした「クールビズ」政策から広まりました 。
暖房の推奨温度(環境省は20℃、WHOなどの機関は少なくとも18℃)は、「これ以下に下げてはいけない」という、人の命と健康を守るための「安全ライン」としての役割が圧倒的に重要です。
いずれも、私たちが快適を感じる温度という事ではありません。
同じ「20℃台」の温度なのに、冷房の26℃は寒く感じ、暖房の23℃は暑く感じる?
同じ「20℃台」の温度なのに、冷房の26℃は寒く感じ、暖房の23℃は暑く感じるという感覚は、多くの人が抱くごく自然な現象です。
これは、エアコンの設定温度だけでは私たちの「体感温度」は決まらないという、室内環境の複雑さに原因があります。
私たちが快適かどうかを感じる要因は、主に以下の3つの大きな違いによって生じます。
- 湿度(湿気が体温の奪われ方を変える)
- 周囲の壁や窓の温度(輻射熱の影響)
- 服装の量の違い
1. 湿度(湿気が体温の奪われ方を変える)
これが冷房と暖房で体感が大きく異なる最大の理由です。
エアコンは運転時に湿度を変化させる性質があります。
| 季節 | エアコンの作用 | 湿度の影響 | 体感温度への影響 |
| 夏(冷房) | 湿気を取る(除湿) | 湿度が下がる | 湿度が下がると、汗が蒸発しやすくなり、体から熱が奪われやすくなります 。 |
| 冬(暖房) | 湿度を下げる(乾燥させる) | 乾燥しすぎる | 暖房で空気が乾燥しすぎると、肌や粘膜から水分が奪われ、実温以上に寒く感じやすくなります 。 |
冷房の26℃が寒く感じるのは、空気が冷たい上に、除湿効果で湿度が下がり、体温が奪われやすくなっているためです。
設定温度以上に涼しく(寒く)感じてしまうのです。
一方、暖房の23℃が暑く感じるのは、冬場は一般的に厚着(ウォームビズ)をしているため、体温が服の中にこもりやすく、少し設定温度を上げるだけで、すぐに「暑い」と感じてしまうためです。
2. 周囲の壁や窓の温度(輻射熱の影響)
体感温度は、空気の温度だけでなく、周囲の壁、床、窓などから発せられる熱の影響(輻射熱)を強く受けます 。
| 季節 | 周囲の環境 | 輻射熱の影響 | 体感温度への影響 |
| 夏(冷房) | 外の壁や窓は熱い | 外からの熱が伝わってくる | エアコンで空気を冷やしても、窓や壁が熱いと、体は「熱いものに囲まれている」と感じて、設定温度より暑く感じやすいです 。 |
| 冬(暖房) | 外の壁や窓は冷たい | 冷気が伝わってくる | 暖房で空気を温めても、窓や壁が冷え切っていると、そこから冷たい輻射熱が体に向かって放出されます。このため、設定温度が23℃と高めでも、体感としては寒く感じやすいのです 。 |
暖房で23℃に設定しても暑く感じたということは、部屋の断熱性が比較的高く、壁や窓から冷たい熱が伝わってこないか、厚着によって完全に熱が保たれている状態だと考えられます。
3. 服装の量の違い
これは最も単純ですが、体感温度を大きく左右する要因です。
- 冷房時(26℃): 夏場は基本的に薄着(クールビズ)のため、体の熱が外に逃げやすく、26℃でも寒さを感じやすいです。
- 暖房時(23℃): 冬場は厚着(ウォームビズ)をしているため、服が断熱材となって体温をしっかりと保温します。そのため、23℃という高めの温度になると、服の中に熱がこもりすぎてすぐに暑いと感じてしまうのです。
これらの要因が組み合わさるため、同じ「23℃」という数値でも、
- 冬の厚着・乾燥した部屋 + 暖かい壁 → 暑い
- 夏の薄着・高湿度な部屋 + 熱い壁 → 快適
といったように、体感が全く異なってくるのです。
快適な温度を見つけるには、設定温度だけでなく、湿度と服装を調整することが鍵となります 。
暖房効率アップでエアコンにかかる電気代いくらに?つけっぱなしでも☺️
実践!電気代を劇的に下げるための「暖房効率アップ術」
エアコンの電気代を削減する上で最も効果的なのは、設定温度を下げることではなく、エアコンが持つ本来の性能を最大限に引き出すことです。
以下に、すぐに実践できる暖房効率アップ術を、その効果とともに解説します。
最高の費用対効果(ROI):フィルター掃除の驚異的な効果
数ある節約術の中でも、フィルター掃除は費用ゼロで、劇的な効果を発揮します。(フィルターに埃が溜まっていた時)
フィルター掃除の節電効果の数値化:
エアコンのフィルターに埃が溜まっている状態(掃除なし)で運転すると、掃除をした場合に比べて消費電力量に約48.9%ものムダが発生していることが実験で示されています。
これは月間換算で約800円の電気料金削減に直結する効果です。
別の調査でも約3割の節約効果があるとされており 、その効果の高さは疑う余地がありません。
フィルターが汚れていると、空気を吸い込む量が少なくなり、部屋を暖める力が小さくなるため、非効率な運転が続きます。
この約50%近いムダは、エアコンが本来発揮できる性能の半分近くを、汚れによって浪費していることを意味します。
このため、フィルター自動掃除機能が搭載されていない機種を使用している場合は、2週間に一度を目安に清掃することが強く推奨されます。
これは単なる節約術ではなく、機器の効率を回復させ、異音や異常振動といった故障リスクを軽減するための重要な日常メンテナンスでもあります。
設定温度 1℃の重み
設定温度の調整は、フィルター掃除に次いで効果が高く、かつ簡単にできる節約行動です。
効果と推奨温度:
暖房時に設定温度を1℃下げると、約10%の節電効果が得られるとされています。
この10%という節約効果は、先に算出したつけっぱなし運転の月間コスト(新型で約12,420円)に当てはめると、約1,240円の削減に相当します。
環境省は、暖房時の室温として20℃を目安に推奨しています。
快適性と健康維持の観点から、設定温度を下げすぎて室温が低くなりすぎないよう、この20℃程度を目標にすることが重要です。
寒く感じる場合は、厚着をする、首・手首・足首などの「首」が付く部分を保温するなどの工夫を行うことで、無理のない範囲で温度調整が可能です。
空気を操る:風量・風向・補助アイテムの活用
暖かい空気は上に、冷たい空気は下にたまるという性質(空気の性質)を理解し、風向きや風量を調整することで、暖房の効率を大きく高めることができます。
暖房の効率を上げる節約アクションと削減効果
| 節約アクション | 想定される節電効果 | 具体的な行動 |
| フィルターを定期的に掃除する | 最大約48.9% (ムダな消費電力を削減) | 2週間に一度の頻度で清掃する |
| 設定温度を1℃下げる | 約10%の電気代削減 | 環境省推奨の20℃を目安に設定する |
| サーキュレーターを併用する | 暖房効率を大幅アップ | 暖かい空気を天井から床へ攪拌し、温度ムラを解消する |
| 断熱カーテン・ブラインドを利用 | 熱の流出入を抑制 | 窓からの冷気侵入・暖気流出を防ぐ |
住宅環境と室外機のケア
エアコンの効率は、部屋の外の環境によっても大きく左右されます。
エアコン暖房以外の暖房器具とのコスト比較と使い分け戦略
エアコンは部屋全体を効率的に暖めることができますが、他の暖房器具を併用することで、より快適に、かつ経済的に冬を過ごすことが可能です。
他の暖房器具のコスト実態
| 暖房器具 | 消費電力の目安 | 電気代の目安 (1時間あたり) |
| エアコン(定格) | 440W~1,060W | 約13.6円~32.8円 |
| パネルヒーター | 約300W~1,200W | 約9円~37円 |
| セラミックファンヒーター | 約450W~1,300W | 約14円~40円 |
| ホットカーペット(1畳用) | 約220W~300W | 約6.8円~9.3円 |
| こたつ | 約80W~600W | 約2円~19円 |
セラミックファンヒーターは、弱運転で使用する限りはエアコンよりも電気代が安くなる可能性があります。
しかし、部屋全体を温めようとして強運転にすると、消費電力が1,300Wに達することもあり、結果的にエアコンより高くつく可能性が高いです。
また、ホットカーペットは、電熱線を発熱させて足元を暖めるため、エアコンの温風が届きにくい場所を局所的に暖める際に有効であり、1時間あたりのコストも比較的低く抑えられます。
石油ファンヒーターは、電気代は安いものの、灯油代を含めたトータルコストで判断する必要があります。
総合暖房戦略:ハイブリッド運用
電気代を抑えつつ快適性を高める最適な戦略は、「主役」であるエアコンと、「補助」の暖房器具を組み合わせるハイブリッド運用です。
- 主役(エアコン): 帰宅時や朝など、室温が大きく下がっているときには、エアコンを使い、部屋全体を素早く設定温度(20℃)まで温めます。
- 補助(ホットカーペット、こたつ): 室温が安定したら、エアコンの設定温度を控えめにするか、定格運転を維持させます。そして、人がいる場所(ソファやデスクの足元)だけを、ホットカーペットやこたつなどの局所暖房で補うことで、体感温度を上げ、エアコンがフル稼働する時間を最小限に抑えることができます。
2025年おすすめの省エネエアコンで電気代節約対策
パナソニック「エオリア HXシリーズ CS-254DHX」
ダイキン「うるさらX RXシリーズ S254ATRS」
まとめ:電気代いくらになる?エアコンの暖房を1ヶ月つけっぱなし
エアコン暖房を1ヶ月つけっぱなしにした場合のコストは、機種や環境によって大きく変動しますが、新型機種であっても月額12,000円を超える大きな費用となります。
このコスト不安を解消するためには、ライフスタイルと住環境に応じた賢い戦略が必要です。
まず、最も優先すべき行動は、費用をかけずに大きな節約効果が得られる「フィルター掃除(約50%のムダ削減)」と、健康を維持しながら実施できる「設定温度20℃の維持(10%節約)」です。
次に、つけっぱなしとオンオフの判断基準として、「外気温3℃ルール」を理解し、特に断熱性が低い住宅や、1〜2時間以上の外出が多い場合は、こまめなオンオフ運転が有利であると判断すべきです。
そして最後に、もし現在旧型のエアコンを使用している場合、新型機種との年間約2万円のコスト差を考慮すると、省エネ機種への買い替えを真剣に検討する時期にきていると言えます。
関連記事